公開:2023/05/16
更新:2024/12/18
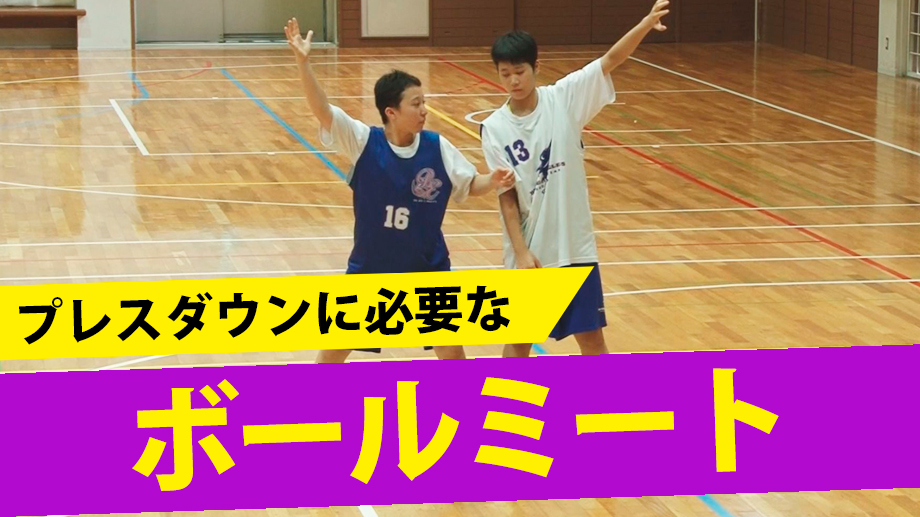
パスがうまくもらえるかどうかは、ボールミートの基本が身についているかどうかで決まります。今回は、ボールミートの原則的テクニックとその練習法について、愛知の名指導・鷲野鋭久氏の指導監修のもとジャパンライムで制作されたコンテンツ「ジュニア世代における合理性・効率性を追求したバスケ指導」から抜粋して紹介します。
鷲野氏は、ディフェンダーがいるとなぜパスをもらいにくくなるのか、そして、ディフェンダーを振り切ってパスを確実にもらうためにはどのような動きをすればよいのかについて、中学生年代にもわかりやすい言葉で段階的に解説しています(以下、鷲野氏の指導内容を要約)。
強いチームはボール運びの精度が高い
きちんとボール運びができるかできないか、でチームの競技力に大きな差が生まれる。バスケットに向かってボールを運ぶ際、一つ一つのパスが成功するかどうかが、オフェンスの成功率に直結する。
パスの「もらい方」つまりボールミートがうまくいかない典型例の一つは、ディフェンスにパスラインを潰され、サイドライン際に追い込まれるケース。このシチュエーションは実際のゲームではよく起こる。このような事態を防ぐために、パスレシーバーが実行すべきテクニックには、4つの基本原則がある。
4つの基本原則
【面取りミート】ディフェンダーを背中で押さえて、ディフェンダーが届かないところに出されたパスを取りに行く(図1)。

【面取りブラインド】面取りミートでレシーブしようするがディフェンダーがオーバーガーディングしてきてスペースを得られない場合は、反転し、相手の裏をついてパスをもらう(図2)。

【インライン振り切り】それでもミートできない場合は、ディフェンダーの死角を利用して切り返し、一気に振り切る(図3)。

【面取り→面取り裏】または面取りをした裏で相手を押さえたうえで、もう一度面取りをして、ディフェンダーが届かない位置でパスを受ける(図4)。

パッシングダウンドリル
これらの原則を身体で覚えるために、2対2、ドリブルなしでパッシングダウンしていくドリルを行う。図5は面取りブラインド、図6はインライン振り切りパターンをそれぞれ実行している例。


ベースラインからスタートし、4つの基本原則パターンの動きを確認しながらパッシングダウンし、反対側のバスケットへのシュートで終わる。ドリブルなしで行う理由は、ディフェンス有利の状況をあえてつくるためだ。
〈商品情報〉
上記の内容は、コンテンツタイトル【ジュニア世代における合理性・効率性を追求したバスケ指導】(全3巻)のうちの第2巻【得点力に直結するボール運び】に収録されています。オンデマンド版、DVD版、どちらでも視聴可能です。

コンテンツの主な収録内容
【第1巻】必ず実戦につながる毎日行いたいドリル集
■デイリードリル:コーディネーション的ドリル/インサイドボディコントロールドリル
■実践1on1ドリル:ケースドリル/ドリブルドリル/もらいざまドリルス/リズムドリブル
■Defデイリードリル:Defフットワーク /ステイドリブル
■リバウンド
【第2巻】得点力に直結するボール運び ←今回紹介した内容はココ!
■基本のボール運び:基本のボールミート/プレスの弱点を突く3on3/プレスの弱点を突く4on4
■プレスダウン5on5:基本形/スタック/スティック(基本)/スティック(応用)
【第3巻】イザという時に使える新戦略・戦術
■マンツーマンアタック:フラッシュモーション/LAモーション/スパイラル/ポストエントリー①/ポストエントリー②/セットオフェンス①/セットオフェンス②/セットオフェンス③
■エンドボールシステム
■サイドボールシステム
■指導・解説:鷲野 鋭久(BLUE EAGLES監督)
■実技協力:BLUE EAGLES