公開:2022/11/04
更新:2024/12/18
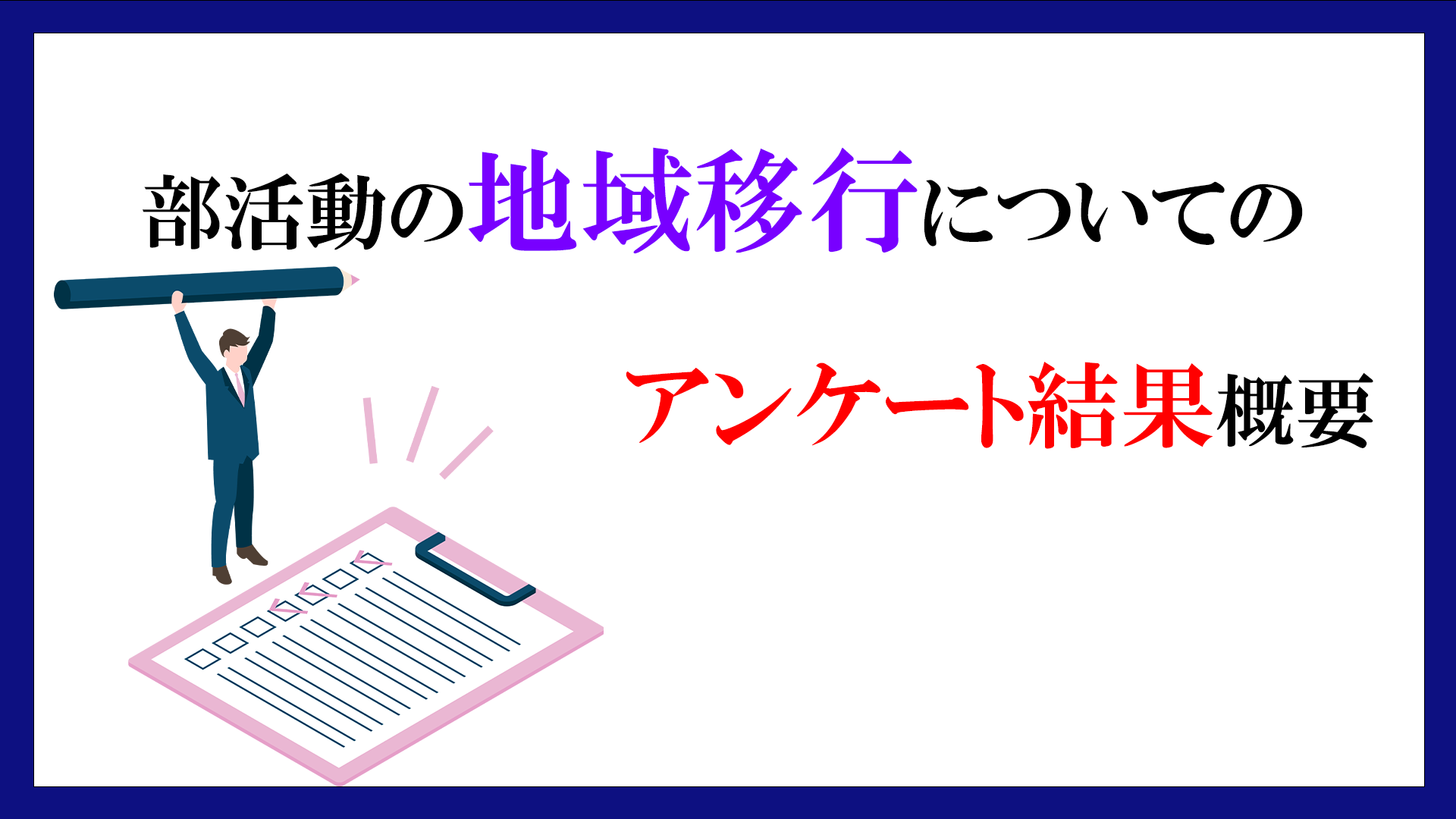
Basketball JUMPでは2022年10月に「部活動の地域移行」をテーマに、全国の指導者の皆様に、現在抱える不安や課題に関するアンケート調査を行いました。この記事では、その結果概要をお伝えします。
地域移行の進行状況
全競技に共通するテーマであるため、今回の調査はバスケットボール以外にも対象を広げ、すべての競技の指導者に対して行いました。50名の方からご回答をいただきましたが、現場指導者の方々が直面している大きな課題であるたけに、皆様の関心は高く、今後表面化するであろう問題、あるいは期待について、具体的なご意見を多数いただきました。
「既に学校では地域移行への取り組みが始まっていますか」
この質問に対しては、予想通り、大半の回答が「いいえ」でした。「はい」は6名(12%)にとどまりました。「はい」とお答えいただいた方の具体例を、以下に挙げます。
(以下、回答例のカッコ内は回答者の指導カテゴリーと、バスケットボール以外の場合は競技名)
・外部講師による指導。(ミニバス)
・土日活動の地域クラブ移行。(ミニバス、中学生クラブチーム)
・部活動指導者が事務局となって活動を管理する形。(中学校部活)
・数年前から、競技専門の教員が配属されない現状があり、学校側からの依頼で地域の各競技団体有志の方がボランティアで指導を行っている。(中学校部活)
・受け皿のを検討している。(中学校部活、陸上競技)
地域移行に期待すること
「地域移行に期待することは何でしょうか」
この質問への回答は、国が進める制度改革への長期的な期待感と、成果を挙げるための実務的な課題を指摘する厳しいご意見が混在する内容となりました。多数意見としては、教員の負担軽減(働き方改革)、指導の質の向上、長期的な視野に立った指導の実現などがありました。以下、回答内容の傾向で、いくつかのカテゴリーに区分けしています。
〈指導の質の向上、効率化〉
・複数の指導者によるチーム運営。(中学校部活)
・不適切な指導を行う教員の淘汰。(中学・高校部活)
・本当にやる気のある子が集まり、少数精鋭でレベルの高い育成年代が出てくる。また、競技を理解した指導者が継続して指導できるので、方針のブレが少なくなる。指導者交代による弱体化がなくなる。(高校部活、硬式野球)
〈子どもたちの競技・練習環境改善〉
・地域の人材活用による子どもたちのスポーツライフの充実。(中学校部活)
・充実した競技環境の整備と、それに対する学校側の協力体制の構築。(ミニバス、中学生クラブチーム)
・生徒の選択肢の増加。(ミニバス)
・子どもたちが好きなスポーツを続けられるようになること。例えば私の地域では、男子バレー部を持つ中学校がないので、育てた選手がバレーを続けることができず、3年間違う部活に所属し、高校でバレーを再開するケースがあり、もったいないとの思いがある。(スポーツ少年団、バレーボール)
・子どもたちが良い指導を受けることができて、その結果として競技力の向上につながっていくこと。(中学校部活)
・子どもがどの学校に入っても専門的な指導が受けられること。(中学校部活)
〈教員の負担軽減〉
・学校、先生方の負担が減ることによる、学校教育現場の改善と向上。(ミニバス、中学校外部指導者)
・大会運営を業者委託する。(高校部活)
・保護者への役割分担。学校の部活動のように学校や顧問にすべて任せるというのでなく、保護者たちと活動を支えていく体制や意識を持っていく必要があると考える。(中学校部活)
〈地域スポーツの活性化〉
・すべての人が幸せになること、大人の都合で子どもの楽しみが減らないようにすること。(中学校部活)
・「おらが村の子どもたち」を地域全体で育てていこうという考えが、より一層広まっていくこと。(中学校部活、バレーボール)
・学校施設の開放。(高校部活、バドミントン)
〈指導者の地位向上〉
・指導者の地位向上・待遇改善。ボランティア活動はやめて、職業として成り立つ仕組みをつくること。(高校、バレーボール)
地域移行への課題は?
制度が変わることで、長期的なメリットを期待する声も多くある一方で、現実問題として具体的な方向性が定まっていないことへの不安、不満も多数ご指摘いただきました。スポーツの技術指導という側面にとどまらず、生活指導や大会運営といった広範な教育・マネジメント業務も包括された形で、従来の学校内部活動は運営されています。地域移行された際、それらの切り分け・分担、あるいは連携をどのように行うのか、といった大きな問題が存在することが、にじみ出るアンケート結果となりました。
以下、地域移行への不安や課題としてご記載いただいたご意見を紹介します。前項と同様、いくつかのカテゴリーに分類しました。
〈学校と外部の連携・分担、指導の一貫性〉
・教員と外部指導員との連携。生徒のこと(性格、家庭環境等)をどこまで共有するのか。外部指導者にどこまでの権限を与えるのか。(ミニバス)
・現状の仕組みであれば、平日は教員が、土日祝日は地域人材を活用してチーム運営が行われると思います。いかなる指導にも一貫性は必要です。一貫性のある指導があるからこそ、学習の積み上げがあり、定着や応用、工夫と言った学習効果が得られると確信しています。(中学校部活、中学生クラブチーム)
〈予算確保〉
・学校側がどこまで予算を出せるか。国や市も予算をどう考えて地域移行させられるか。(ミニバス、中高クラブ)
・クラブチーム等の勝利至上主義が広がり、底辺拡大につながらないこと。(ミニバス)
・持続性のある地域移行にならないと衰退が加速する。(ミニバス、中学生クラブチーム)
・謝金の財源が学校として確保できるのか。外部指導者はボランティアというわけにはいかない。(スポーツ少年団、バレーボール)
〈練習場、移動など物理的問題〉
・練習場の確保が難しい。学校が外部の団体に対して施設を貸し出すことを躊躇している所が多い。(ミニバス、中学生クラブチーム)
・体育館の割り振り。通常の活動場所から外部に出ての活動は可能か?(中学校)
・選手や保護者の費用・送迎等の負担が増えて、結果競技離れにつながるのではないか。地域スポーツに関わる教員は、結果としてよりブラックな労働環境になっていくのではないか。(中学校)
〈大会・競技運営〉
・今後の大会はどうなっていくのか。中体連はどうなる?(中学校)
・クラブチームの運営がボランティアベースで、大会運営に協力できるレベルに達していない。コーチング、レフェリング、リスクマネジメントなど学べていない状態で参入してきており、中体連の一部に負担のしわ寄せがいく。(中高部活)
・大会運営が残ると、負担は変わらないと思う。(高校)
・大会の形式を先に示してほしい。(中学校、陸上競技)
〈指導者の確保〉
・地域に指導者がいないとそのスポーツは廃れていくのではないか。今後、どうすそ野を広げていけるのか。(高校、バレーボール)
・公式戦の引率はどうなるのか。地域移行すると土日の公式戦に協力しない教員が多くなる可能性が大きい。(高校、ラグビー)
・指導者数の確保と練習場所の不足。(中学生クラブチーム)
・外部にやりたい人がいない。地域移行を主導する人がいない。(中学校)
〈家庭の経済格差による影響〉
・スポーツを始めるきっかけが部活動であると思うが、お金がかかるとなるとハードルが高くなってしまう懸念。(中学校、バレーボール)
・経済格差でクラブに参加できない子の活動機会はどうするのか。(中学校、バレーボール)
〈その他〉
・将来的に競技人口減少の懸念。(中学校)
・ケガや事故、トラブルへの対応およびその責任の所在。(中学校)
・団体戦出場など人数確保のためにクラブチーム間で選手の奪い合いが起きるのではないか。(中学校、卓球)
・外部クラブチームによる子どもの取り合い。委託先の取り合い。委託先への丸投げの不安。(ミニバス、中学校外部コーチ)
部活動地域移行は、社会全体にとっても大きな課題であり、日本のスポーツが今後どう変わっていくか、を左右する一大変革と言っても過言ではありません。Basketball JUMPでは、今後もこのテーマを追い、事例紹介などを展開していきたいと思います。